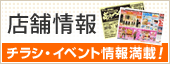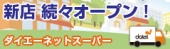1年の無病息災を願って食べる「七草粥」の由来をご存じですか?
1月7日は、1年で最初の節句である「人日(じんじつ)の節句」です。「人日」とは人を大切にする日という意味で、かつての中国ではこの日に7種の野菜を入れた汁物を食べ、無病息災や立身出世を祈ったといわれています。
そもそも日本には、年のはじめに若草を摘んで食べる「若草摘み」という風習がありました。現代ではお正月は冬ですが、旧暦では春。そのため長い冬をじっと耐え、ようやく芽吹いた春の若草を食べることでその生命力が取り入れられ、無病息災に通じると考えたわけです。
この「若草摘み」と「人日」が結びついたのが、「七草粥」の伝統行事。1月7日の朝、春の七草と呼ばれる7種の野菜を入れたお粥を食べて1年の無病息災を願います。消化のよい「七草粥」は、お正月のごちそうで疲れた胃腸をいたわる昔の人の知恵でもあるようです。
春の七草を覚えよう
「春の七草」は5・7・5・7・7の短歌のリズムで覚えるのがコツ。『せりなずな・ごぎょうはこべら・ほとけのざ・すずなすずしろ・はるのななくさ』と、子どもと一緒に口ずさみながら、「七草粥」を作ってみませんか。