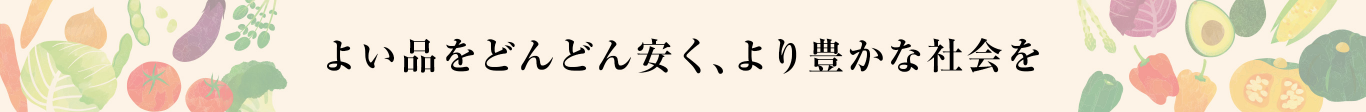ひなまつりの歴史
ひなまつりの起源は平安時代。3月の最初の巳(み)の日に、わが身にふりかかる災いを人形(ひとがた)に託して川や海に流した行事がはじまりとされています。その頃、貴族の家の少女たちの間では「ひいな」と呼ばれる人形遊びが行われており、こうした行事と遊びが結びついて「流しびな」が誕生したのだそうです。さらに江戸時代には人形作りの技術が向上し、家の中に人形を飾る、現在のようなひなまつりの形になりました。
ひなまつりの祝い料理
ひなまつりの祝い料理には、それぞれに縁起の良い意味がこめられています。夫婦が仲良く添いとげるようにと願った縁起物の「はまぐり」。“寿(ことぶき)を司(つかさど)る”として昔から祝いの席で食べられてきた「ちらし寿司」は、縁起の良い食材などを使って彩りも華やかに。そして「ひなあられ」は桃・緑・黄・白の4色で 四季をあらわすという説があり、娘が1年中幸せに過ごせるようにとの願いをこめたものだとか。