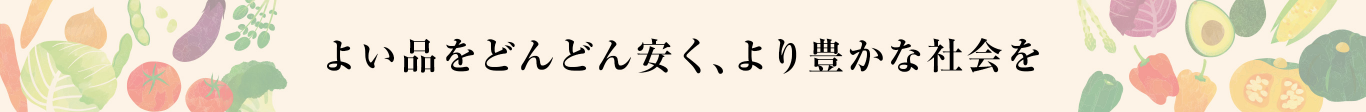お正月とおせち料理
お正月は歳神様を迎える大切な儀式
お正月はもともと五穀の神様である歳神様を迎え、その年の豊作を祈る儀式。門松、しめ飾り、お鏡餅、おせち料理などをすべて神様をお迎えするための準備です。
おせち料理は本来、五節句(1/7人日、3/3上巳、5/5端午、7/7七夕、9/9重陽)に豊作や健康を願う「節会(せちえ)」という朝廷の宴会で出された祝い膳のことで、「煮染め」がその原形です。
その後、大名の参勤交代の弁当用に、ぎっしりと保存食をつめた「重詰め」が考案され、それが一般に広まって現在のようなかたちになりました。
「おせち」は主婦をねぎらい、家族の健康を祈るためのごちそう。
日本人の生活もずいぶん様変わりし、お正月料理本来の意味も薄れてきましたが、年の初めにみんなで食卓を囲んで一年の健康と幸せを祈るゆとりある時間は、いつまでも大切にしたい素敵な文化です。
お正月料理は神様を迎える時に台所仕事などで騒がしくしないこと、日頃の主婦の労をねぎらう保存食という複数の意味をもち、神様にお供えしたものは御利益にあやかるため、みんなでいただきます。
年の初めは安心できる食生活、健康について改めて考えるよい機会でもありますね。
おすすめメニュー
一年の健康と安全の願いをこめて。
ご家庭で「手作りおせち」にチャレンジしてみませんか。
梅酢れんこん

◆れんこんの穴を通して向こうが見えるということから、“先の見通しがきく”という意味をもちます。酢の物だけでなく、煮染めにも欠かせないお正月に大活躍の根菜です。
●作り方
- 1)
- れんこんは“花れんこん”にし、7~8mm厚さに切って酢水にさらす。
- 2)
- 梅干しは種を取って果肉を裏ごし、酢、砂糖、煮きりみりん、塩と混ぜ合わせて梅酢を作る。
- 3)
- 1)のれんこんを少量の酢を加えた熱湯で歯ごたえが残るようにゆで、熱いうちに2)の梅酢に漬け込んで味をなじませる。
●材料
| れんこん | 1/2節 |
| 梅酢 | |
| 紀州南高梅 | 3~4個 |
| 酢 | 大さじ3 |
| 砂糖 | 大さじ2 |
| 煮きりみりん | 大さじ2 |
| 塩 | 小さじ1/4 |
| 酢 | 適量 |
花れんこんの作り方
- れんこんは5cm長さに切り、穴と穴の間に切り込みを入れる。

- 穴山から切り込みに向かって切り落とし、れんこんを逆向きに持ちかえ、反対側も同様に切り落とす。

- 穴にそって形を整え、食べやすい厚さに輪切りにする。

煮染め

◆冬に旬を迎え、おいしさも栄養価もとびきりの根菜を集めた“煮染め”は、おせち料理の基本です。
●作り方
●材料
| 鶏もも肉 | 200g |
| にんじん | 1本 |
| れんこん | 1/2節 |
| ごぼう | 1本 |
| 生芋こんにゃく | 1/2枚 |
| 煮汁 | |
| だし汁 | 2・1/2カップ |
| 酒 | 大さじ3 |
| 砂糖 | 大さじ3 |
| みりん | 大さじ1 |
| しょうゆ | 大さじ3 |
| サラダ油 | 大さじ1・1/2 |
| 酢 | 適量 |
ねじ梅の作り方
- にんじんは1cm厚さの輪切りにして、梅の抜き型で抜く。

- 花の中心に向かって、花びらと花びらの間に切り込みを入れる。

- 切り込みから次の切り込みの中央に向かって斜めに切り落とし、これをくり返す。

手綱こんにゃくの作り方
- こんにゃくはゆでて水気を切り、小口から7~8mmの厚さに切る。

- 中央に横長に3cmくらいの切り込みを入れる。

- 片端を中央の切り込みにくぐらせ両端をもって軽くひっぱる。

松茸小芋の揚げ煮

◆小芋がたくさんつく里いもは子孫繁栄の象徴とされます。親芋は、かしら芋とも呼ばれ、「頭(かしら)」になるようにという願いもこめられます。
●作り方
- 1)
- 里いもは“松茸小芋”にむいて水からゆで、煮立ったら水でぬめりを洗い落とす。
- 2)
- 水気をしっかりとふき取ってから160度に熱した揚げ油できつね色に揚げたあと、ザルに広げて熱湯をかけて油抜きにする。
- 3)
- 鍋に煮汁を入れて火にかけ、ひと煮立ちしたら2)の里いもを入れて煮含める。
●材料
| 里いも | 8個 |
| 煮汁 | |
| だし汁 | 1・1/2カップ |
| みりん | 1/4カップ |
| 酒 | 1/4カップ |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| しょうゆ | 大さじ3 |
| 揚げ油 | 適量 |
松茸小芋の作り方
- 里いもは丸い方の部分の皮の1/3ほどの周囲にクルリと浅く切り込みを入れる。

- 笠の部分を残すよう、根元に向かって六方に皮をむく。


管ごぼうの煮物

◆地中に根を張るごぼうに新年の決意、芯を抜き取り見通しをよくすることで見通しをよくする意味も加わります。ごぼうは皮のまわりが特においしいとされ、管ごぼうは“いいとこ取り”の食べ方だと言われています。皮側と内側は違った種類の繊維質なので、すっぽりときれいに抜くことができます。
●作り方
- 1)
- ごぼうは“管ごぼう”にし、酢水にさらしてアクを抜く。
- 2)
- 鍋に煮汁を入れて火にかけ、1)のごぼうを入れて煮含める。
●材料
| ごぼう | 1本 |
| 煮汁 | |
| だし汁 | 1・1/2カップ |
| みりん | 大さじ1 |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| しょうゆ | 大さじ1・1/2 |
| 酢 | 適量 |
管ごぼうの作り方
- ごぼうはたわして軽く洗い、4cm長さに切って酢水にさらしてアクを抜く。

- 熱湯に少量の酢を入れた中でサッとゆで、ザルに上げて水気を切る。
- 切り口の皮から一回り内側の筋に金串を刺し、ぐるっと一回りして芯を抜く。

田作り

◆干したカタクチイワシを甘くからめた田作り。カタクチイワシを肥料にしたところ大豊作になったということから、五万米(ごまめ)ともいわれます。
●材料
田作り50g/タレ[しょうゆ・みりん各大さじ2、砂糖大さじ1、水あめ小さじ1]/酒大さじ2/白炒りごま大さじ1
●作り方
- 1)
- 田作りは耐熱皿に広げ、ラップをせずに電子レンジ強で1分30秒~2分加熱する。(1本取り出し少し冷まし、ポキッと折れるぐらいまで加熱する。)
- 2)
- 鍋にタレを合わせて中火で少し煮詰め、1)を加えて手早く混ぜ、酒を振って火からはずして全体にからめ、最後に白炒りごまを混ぜてバットや皿などに広げて冷ます。
いくらの柚釜

◆美しく輝くいくらを財宝に見立てて豊かな一年を祈るものです。魚の卵の類は一尾からとれる数も多いので、子孫繁栄の象徴としておめでたい席によく登場します。
●材料
柚子1個/塩いくら130g/漬け汁[みりん小さじ1、酒大さじ1、薄口しょうゆ小さじ1]
●作り方
- 1)
- 漬け汁の調味料を合わせてひと煮立ちさせ、冷ましてからいくらを漬けて味をなじませる。
- 2)
- 柚子の上部を切りとって中身をくり抜き釜を作り、1)のいくらを盛り込む。
数の子

◆アイヌ語でニシンのことをカドといい、カドの子がなまって数の子に。二親(ニシン)から、たくさんの子が生まれるという縁起ものです。
●材料
 数の子300g/漬け汁[だし汁1・1/2カップ、酒大さじ3、みりん大さじ6、しょうゆ大さじ6、花かつおひとつかみ]/塩適量
数の子300g/漬け汁[だし汁1・1/2カップ、酒大さじ3、みりん大さじ6、しょうゆ大さじ6、花かつおひとつかみ]/塩適量
●作り方
- 1)
- 水3Lに小さじ2杯強(約9g)の食塩を溶かし、数の子を3時間浸す。その後、2時間ごとに全部で3~5回、1)の食塩水をとりかえ、最後に表面のうすい膜を取り除く。
- 2)
- 鍋に漬け汁を合わせて火にかけ、ひと煮立ちしたら花かつおを加えてサッと煮、こして冷ます。
- 3)
- 1)の数の子の水気をふき取って2)の漬け汁に3~4時間以上漬けて味をなじませる。
かまぼこ

◆紅は“魔よけ”を、白は“神聖”の色。紅白の組み合わせで、紅が白を守る意味があります。

![]()
- 1)
- 蒲鉾は1cm厚さに切り、皮をむくように表面を端から七分目までそぎ切る。
![]()
- 2)
- 中央に横長に3cmくらいの切り込みを入れる。
![]()
- 3)
- 片端を中央の切り込みにくぐらせ両端をもって軽くひっぱり表面にぴったり重ねる。


- 1)
- 板についたままのかまぼこの向こう側をおさえ、包丁を斜めに入れる。

- 2)
- 包丁の先が動かないようしっかり押さえながら、包丁を左右に小刻みに動かして切る。
![]()
- 3)
- 波形に切った部分から順に、かまぼこを板から切りはなす。
紅白巻き

◆薄紅色のサーモンが、いかにも春らしい表情を食卓に添える一品。
●材料
スモークサーモン16枚/大根8cm長さ/A[塩大さじ1、昆布だし3カップ]甘酢[酢大さじ3、柚子の絞り汁大さじ2、砂糖大さじ2、塩小さじ1/5]
●作り方
- 1)
- 大根は厚めに桂むきし、4等分の長さに切ってからAにつけ、しんなりしたら水気をふき取って甘酢に漬ける。
- 2)
- 1)の大根の汁気をふいて巻きすの上に広げ、スモークサーモン4枚を上に並べ、“の”の字に巻き込む。残りも同様にし、それぞれ食べやすい大きさに切る。
鶏の松風焼き

◆みそを使った茶色の仕上がりを、風雨に耐えて寿命が長い、おめでたい松の木に見立てたものです。
●材料(14cm×11cm×4.5cmの流し缶1個分)
鶏むね挽肉400g/たまご1個/おろししょうが15g/こうじみそ40g/酒大さじ1/砂糖大さじ1/しょうゆ大さじ1/2/片栗粉大さじ1/2/けしの実適量/サラダ油適量
●作り方
- 1)
- ボウルに鶏挽肉、みそ、しょうゆを加え、粘りが出るまでよく練ったあと、卵、おろししょうが、酒、砂糖、片栗粉を加えて混ぜ合わせる。
- 2)
- 流し缶にサラダ油を薄く塗って1)の生地を流し込み、中央を少しくぼませるようにして表面をならし、けしの実を振る。
- 3)
- 180度に熱したオーブンで約20分焼き、冷ましてから食べやすい大きさに切る。
りんご入りきんとん

◆“金団”と書いてきんとんと読み、きれいな黄金色を財宝に見立てて豊かな一年を祈るものです。砂糖が貴重だった昔は大変な贅沢品でした。より美しい黄金色に仕上げるために、くちなしの実で色をつけることもあります。
●材料(4人分)
さつまいも600g/りんご1/2個/レモン汁大さじ2/砂糖150g
●作り方
- 1)
- さつまいもは3cm幅の輪切りにして皮を厚くむき、水にさらしてアクを抜いたあと、鍋に入れて水をひたひたに注ぎ、中火でやわらかくなるまでゆで、熱いうちに裏ごす。
- 2)
- りんごはきれいに洗い、皮つきのまま2~3mm厚さのいちょう切りにし、レモン汁をまぶす。
- 3)
- 鍋に2)を汁ごと入れて砂糖を加え、りんごがしんなりするまで中火で煮、1)を加えて弱火で焦がさないように練り上げる。
たたきごぼう

◆ごぼうの色を豊作の時に飛来するとされる黒い瑞鳥に見立てて豊作を願うものです。また、細く長く地中に根を張るごぼうに、しっかりと新しい年の暮らしをたてていくという一年の決意をこめる意味も。
●材料(4人分)
ごぼう200g/和え衣[白ごま(すったもの)大さじ5、酢大さじ3、砂糖大さじ2・1/2、塩小さじ1/2]/酢適量
●作り方
- 1)
- 調味料を混ぜ合わせて和え衣を作る。
- 2)
- ごぼうは皮をこそげて鍋に入る長さに切り、少量の酢を加えた熱湯でゆで、すりこ木でたたいてから4cm長さに切り、温かいうちに1)の衣で和える。
煮しめ

◆冬に旬を迎え、おいしさも栄養価もとびきりの根菜を集めた“煮しめ”は冷めてもおいしくいただける優秀な保存食です。その昔、節会(せちえ)という行事で供された、おせち料理のルーツです。
●材料(4人分)
鶏もも肉200g/れんこん1/2節/ごぼう1本/里いも4個/にんじん1本/たけのこの水煮200g/生芋こんにゃく1/2丁/煮汁[だし汁3カップ、酒・砂糖・しょうゆ各大さじ3、みりん大さじ1]/サラダ油大さじ1・1/2/酢適量
●作り方
- 1)
- 鶏肉は一口大に切る。れんこんは“花れんこん”にしてから縦半分に切り、7~8mm厚さに切る。ごぼうは5mm厚さの斜め切りにして酢水にさらす。里いもは皮をむいて下ゆでする。にんじんは“ねじ梅”にする。たけのこは穂先の方をくし形に切り、根元の方は半月切りにする。こんにゃくは“手綱こんにゃく”にしてゆでてアクを抜く。
- 2)
- 1)をサラダ油で炒め合わせてから出し汁を加え、ひと煮立ちしたらアクを取り、しょうゆ以外の調味料を加えてしばらく煮たあと、しょうゆを2回に分けて加え、煮汁がなくなるまで煮含める。