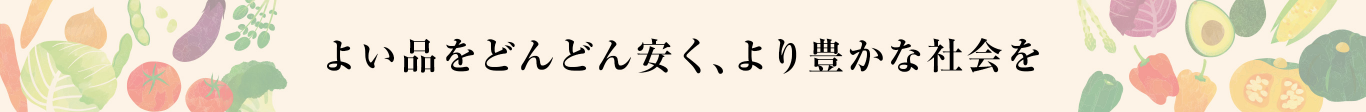平安時代、貴族の子どもたちの間では、紙の人形を使った「ひいな遊び」が盛んにおこなわれていました。この人形に自分自身の災厄をうつして川や海に流して清める、「流しびな」という行事が「ひなまつり」の起源といわれています。現代の「ひなまつり」は、女の子の健やかな成長をお祝いする日。ひな人形を飾り、はまぐりのお吸い物やちらし寿司、ひし餅、ひなあられなどを食べてお祝いするのが習わしです。
ひなまつり料理の由来をご存じですか?
ちらし寿司
“寿(ことぶき)を司(つかさど)る”として、昔からおめでたい席で食べられてきました。えび、錦糸卵、豆などの縁起のよい具材が入った、お祝いにぴったりのお料理です。
はまぐりのお吸い物
二枚貝のはまぐりは、対になる貝殻でなければ形や模様が合わないことから、仲のよい夫婦の象徴とされてきました。ひなまつりでは、よい相手と結ばれることを願って食べられます。