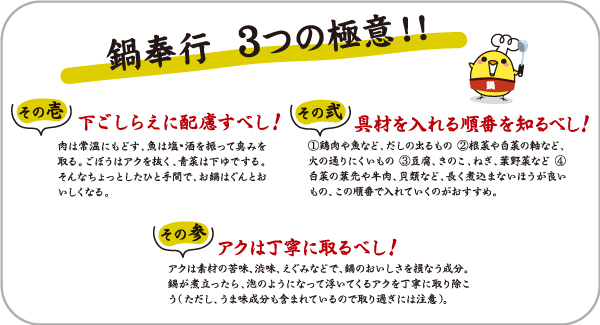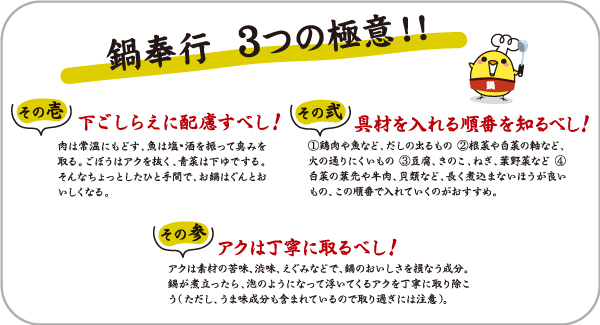肌寒さを感じはじめたら、いよいよお鍋がおいしい季節です。今年は、全国津々浦々の味が楽しめるおいしいご当地鍋に挑戦。味わいさまざま、個性もいろいろ、郷土の味を堪能しましょう。


水炊き(博多風)
鶏肉から出るうま味を生かして、水から煮立たせる「水炊き」。煮汁に味をつけず、ぽん酢しょうゆやつけダレで食べるのが定番です。だしを取るのに鶏の皮や骨を使うことも。


石狩鍋
石狩川の漁師が、釣ったばかりの鮭をぶつ切りにして野菜や豆腐などといっしょに煮込んで食べたのがはじまり。カラダが芯からあたたまる、冬の北海道を代表する料理です。


せんべい汁
八戸市周辺の郷土料理で、南部せんべいを割り入れ、ごぼうやきのこなどの野菜とともに鶏や豚のだしで煮たもの。だしを吸ったせんべいは、すいとんやお麩に似た食感に。


いも煮
里いもと肉を使った具だくさん鍋。東北地方で広く作られており、山形県ではしょうゆ味、宮城県ではみそ味が一般的。秋には河原などで「いも煮会」が盛んに開かれます。


ねぎま鍋
「ねぎ」と「まぐろ」が名前の由来。江戸時代に、保存がきかずに捨てられていたまぐろの脂身(とろ)を利用しようと考えられたもので、濃厚なうま味が人気となりました。


味噌おでん
八丁みそをベースにした甘めのみそダレで、大根、こんにゃく、卵、はんぺんなどの具材をぐつぐつと煮込んだもの。地元では、ご飯のおかずに酒の肴にと大人気です。


湯豆腐
豆腐を昆布だしで煮て、薬味とぽん酢しょうゆでいただく「湯豆腐」は、豆腐そのものの味わいを楽しむ料理。豆腐のおいしさで名高い、京都ならではのシンプルな料理です。


飛鳥鍋
鶏がらのだしに牛乳を加えた、まろやかでコクのある鍋。飛鳥時代に唐から渡ってきた僧侶が、寒さをしのぐために山羊の乳で鍋料理を作ったのがはじまりとされています。


すき焼き(関西風)
関東では「割り下」と呼ばれる鍋つゆで肉を煮ますが、関西では「すき焼き」の名のとおり、肉を焼くのが特長。水分を入れずに、調味料と具材から出る水分だけで調理します。